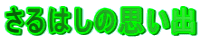 天王山のこと
天王山のこと
「てんのう山」は「天王山」なのか「天皇山」なのか、考えもせず「てんのうやま」と呼んでいた。 猿橋の南側に聳える山である。
旧町役場前あたりから見た天王山 空地は中込商店跡

改めて標高を調べて見たら、544m余。 もっと高い山だと思っていたが、町の標高300m余からは標高差240mほどの山である。
伊良原の小学校の奧の方に登山口があった。 猿橋の町から見ると頂上が平らになっている様に見えるたが、登って見ると、さにあらず、大きな石があるだけの山頂で、周囲の木々が髙く、あまり景色が良くなかった記憶がある。
子供の頃、近所の仲閒達と弁当を持って登山したことがある。 餅を焼いて、醤油をかけ海苔を巻いて弁当箱に入れて持って行った。 わずか1,2時間後に食べたのだが、餅がかたまって弁当箱の形になっていた。

伊良原(猿橋小学校の奧の方)に登山口があった。
最近、ネットで検索すると「猿橋 城山」とい記事がいくつかヒットする。読んで見ると、「城山」とは「天王山」の事のようである。大月市郷土資料館の記事にも天王山を「城山」と呼んでいる。最近、山の名前が変わったのだろうか? それとも「城山」が正式名称なのに、それを知らず我々が「てんのうやま」と呼んでいたのだろうか。
城山と呼ばれているせいか、城跡めぐりをしている人達がよく訪れているようで、「猿橋城 岩場に守られた要害」なんていうタイトルのサイトで天王山と思われる山を紹介している。
猿橋城 岩場に守られた要害
天王山に城があったなんて話は聞いた事がない。どこから「城山」という名になり、猿橋城なんて言葉出て来たのだろう。
|
大月市郷土資料館のサイトに「城山」と呼ばれる理由のヒントがあった。
「甲斐国志」巻之五十四 古蹟部第十六之下の猿橋の項に
(猿橋)駅の東南に城山と云う山あり、高さ壱丁ばかり、上平坦にして礎石の跡あり。けだし狼煙火(のろし)台なるべし
という記事があるそうである。
狼煙台と聞くと、なるほどと思う。 岩殿山との間には何の遮るものもなく狼煙で情報を交換できる高さ、位置にある。
狼煙が有力な情報伝達手段であった時代、この位置、高さは重要だっただろう。しかし、「猿橋城」があったのか?。
大月市郷土資料館 「城山にのぼりました」
ネットで探したら、現在の天王山の頂上はこんな景色のようだ。こんなだったかな?、と思う写真だ。

「YAMAP」サイトより
|
ところで、この山(天王山と呼んでおこう)の登山口(猿橋小学校の奧の方)の登り口に小さな神社がある筈だ。 実はこの神社、私の父(明治40年生れ)が、どこか別な所にあった神社の建物を譲り請けて、この地に移築したものだ。 もう20年間も行っていないので、今もあるかどうかわからない。
|
これもネットで調べたら、登山道に赤い鳥居と、右側に何か祠のようなものがが見える。前述の父が作って神社とは違うので、やはりあの神社は朽ちてしまったのだろう。場所が同じかどうかわからない。

|
昭和30年頃、この山頂付近には猿橋町のテレビ共聴アンテナが立っていた。 カメ屋電機が中心となった企業体がこの共同アンテナで受信した東京のテレビ放送をケーブルで町中に配信していた。だから山梨県にありながら、甲府からの放送を見る事ができず、地元のニュースも見る事はなかった。
したがって甲府の方ではNHKと山梨放送(YBS)しかなかった時代に、日本テレビ、TBS、フジテレビ、日本教育テレビ(後のテレビ朝日)も見れたので、甲府の連中に自慢したものだ。



